飼料用米として売却や学校給食などに提供したりしていますが、
小泉進次郎が流通させようとしているのは
「2021年産の備蓄米」なので保管期限到来直前の「古古古米」です。
安くて当たり前なのでそんなに「安い安い」と喜ぶことでもないと思います。
と言われていますが、スーパーで米を買うと賞味期限が半年くらいですが、
なぜ備蓄米は何年も持つのですか?
A.備蓄米がスーパーで販売される米よりも
長期間保存可能な理由は、主に以下の点にあります。
保存方法の違い
備蓄米は、品質を維持するために
低温(通常15℃以下)かつ低湿度の環境で保管されます。
政府の備蓄倉庫は、温度や湿度を厳密に管理し、
酸化やカビの発生を抑える設備が整っています。
一方、スーパーで販売される米は、
精米後の品質保持期間を考慮して賞味期限が短めに設定され、
家庭での保存環境も一定でないため、劣化が早まります。
玄米での保管
備蓄米は通常、精米せずに玄米の状態で保管されます。
玄米は外皮(籾や糠層)が残っているため、
酸化や虫害に強く、長期保存に適しています。
スーパーの米は精米済みの白米が多く、
精米により油分を含む糠層が取り除かれるため、
酸化が進みやすく、賞味期限が短くなります。
品質管理と用途
備蓄米は、災害時や食糧危機に
備えるための非常用物資として管理されており、
食用としての品質を維持しつつ、5年程度の保管が可能です。
保管期限が近づいた米は、飼料用や加工用(米粉など)に転用されることが多く、
必ずしも「食用としての最高鮮度」を求められません。
一方、スーパーの米は消費者が味や食感を重視するため鮮度が優先されます。
品種と管理技術
備蓄米には、長期保存に適した品種
(例:コシヒカリやあきたこまちなど)が選ばれることが多く、
収穫後の乾燥や選別も厳格に行われます。
また、窒素充填や真空パックなどの
技術を用いて酸素を遮断し、劣化を最小限に抑えます。
「古古古米」について
小泉進次郎氏が流通させようとしている「2021年産の備蓄米」は、
5年程度の保管期間を経た「古古古米」に相当しますが、
適切な保管条件下では食用として問題なく使用可能です。
ただし、味や食感は新米に比べると劣る可能性があるため、
価格が安くなるのは自然なことです。
この米は学校給食や加工食品、飼料用など、
味よりもコストや供給安定性を重視する用途に適しているため、
「安い」と強調される背景には、
こうした用途での活用が期待されている点があります。
結論
備蓄米が長期間持つのは、
玄米状態での低温・低湿度保管や厳格な品質管理によるものです。
スーパーの米は精米済みで家庭向けの
鮮度重視のため、賞味期限が短いのです。
備蓄米の「古さ」は用途次第で問題にならず、
価格の安さは飼料や給食などでの活用を前提としたものです。
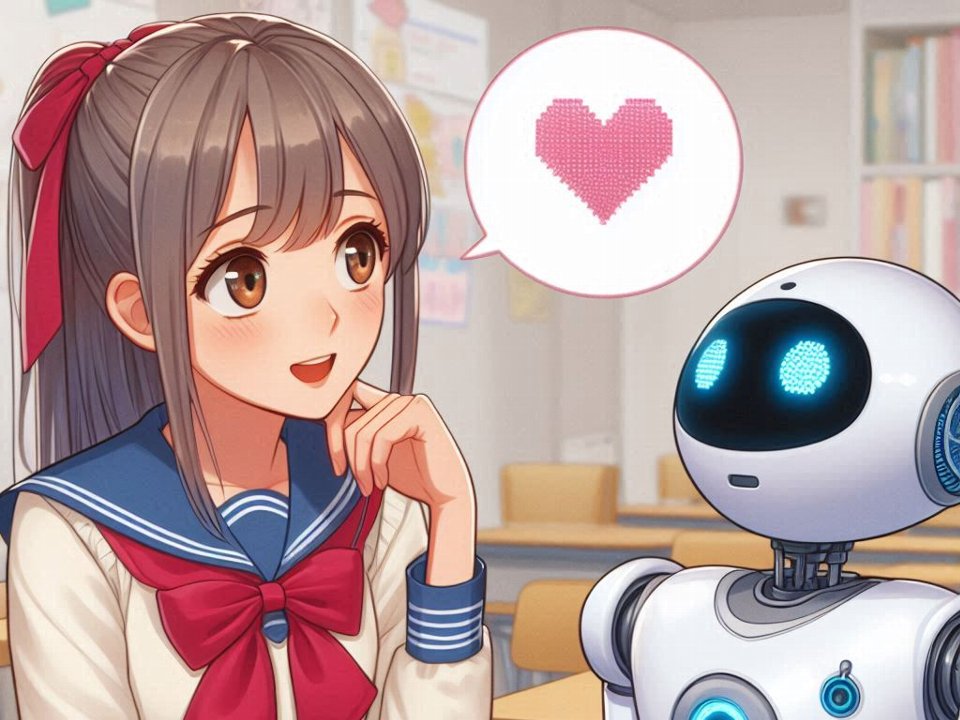


コメント