デビューできなかったり
活躍できず引退した馬の余生が気になります。
乗馬や牧場など引き取り先が
無い馬は処分されてしまうのでしょうか?
毎年、殺処分されてしまう馬は何頭いるのでしょうか?
A.競馬の馬として生まれ、
デビューできなかったり、
活躍できずに引退した馬の余生について、
確かに気になるところですね。
日本における競走馬の引退後の状況について、
できる限り事実に基づいてお答えします。
引退馬の行き先と現実
日本では、競走馬として登録されるサラブレッドは、
毎年約7,000頭前後が生産されています
(日本中央競馬会・JRAや地方競馬のデータに基づく推定)。
これらの馬のうち、競走馬として
デビューできるのは約半数から7割程度で、
残りはレースに出走することなく淘汰されるケースがあります。
また、デビューした馬も成績が振るわなかったり、
怪我などで競走能力を失うと、早い段階で引退となります。
通常、競走馬としての活躍期間は2歳から5~6歳程度で、その後は引退を迎えます。
引退後の馬の行き先としては、
以下のような選択肢があります。
1.繁殖馬
優秀な成績を残した牡馬や牝馬が
種牡馬や繁殖牝馬として牧場で第二の人生を送るケース。
ただし、これはごく一部(年間約1,000頭程度)で、
特に牝馬は繁殖に上がる数が限られます。
2.乗馬クラブやセラピー馬
一部の馬は乗馬用や教育用、
セラピー用として引き取られます。
しかし、サラブレッドは臆病で気性が激しい傾向があり、
乗馬に適さない場合も多く、引き取り先は限定的です。
3.個人や団体による引き取り
引退馬協会や支援団体、
個人が引き取るケースもありますが、
これも全体の数から見れば少数です。
4.屠殺・食用
残念ながら、引き取り先が見つからない馬の多くは屠殺され、
馬肉やペットフードとして加工されます。
日本では馬肉(桜肉)としての需要があり、
経済動物としての側面が強く残っています。
殺処分の現実
「殺処分」という言葉がよく使われますが、
厳密には、競走馬の場合は病気の感染防止
や安楽死(レース中の重傷など)といったケースを除き、
多くは食用目的での「屠殺」です。
ただし、一般的な認識ではこれも
「殺処分」に含まれることが多いため、その文脈で話を進めます。
引退馬の大部分が屠殺に回されるという指摘は、
競馬業界内外で長年議論されてきました。
よく引用される「引退馬の9割が殺処分」という数字は、
ドキュメンタリーや一部の報道で使われたもので、
正確な統計がないため推定値に過ぎません。
しかし、複数の情報源や関係者の証言から、以下の事実が浮かび上がります。
そのうち繁殖や乗馬に進むのは1,000~2,000頭程度。
屠殺に回されている可能性が高いとされています。
デビュー前に淘汰される馬や、地方競馬の馬を含めると、
年間の屠殺数はさらに増えると考えられます。
農林水産省によると、日本で食用に屠畜される馬は
年間約7,000~10,000頭(国産馬と輸入馬の合計)とされ、
その多くが引退した競走馬や乗馬だと推測されています。
具体的な頭数
「毎年、殺処分される馬は何頭か」という問いに対して、
公式な統計が公開されていないため、
正確な数字を出すのは困難です。
しかし、以下のように推定されます。
引退馬の屠殺数
年間約4,000~5,000頭(引退馬全体の6割~8割程度)。
競走馬以外を含む総数
デビューできなかった馬や地方競馬の馬を含めると、
年間7,000頭前後に上るとみられます。
この数字は、引退馬協会や動物福祉団体、
報道などから得られる断片的なデータを総合したものです。
例えば、朝日新聞(2024年4月16日付)では、
「年間8,000頭が生産され、6,000頭が引退し、その大部分が食肉に」
と報じられており、傾向としては一致します。
改善への動き
近年、引退馬の余生を支える取り組みも増えてきました。
NPO法人引退馬協会や民間の養老牧場、
クラウドファンディングを活用したプロジェクトなどが活動を展開し、
乗馬やセラピー馬としての再訓練を行っています。
しかし、馬1頭の飼育には年間50~100万円の費用がかかり、
支援が追いつかないのが現状です。
また、海外(例:アメリカやイギリス)では
屠殺目的の譲渡を禁止する動きがありますが、
日本ではまだ法的な規制がなく、経済的な理由から屠殺が続いています。
結論
引き取り先がない馬は、
残念ながら多くの場合、屠殺されてしまいます。
競馬業界は「馬産振興」を掲げますが、
その裏で多くの馬が短い生涯を終えているのが現実です。
一方で、支援団体や個人の努力により救われる馬も増えつつあり、
関心を持つ人が増えれば状況は変わる可能性もあります。
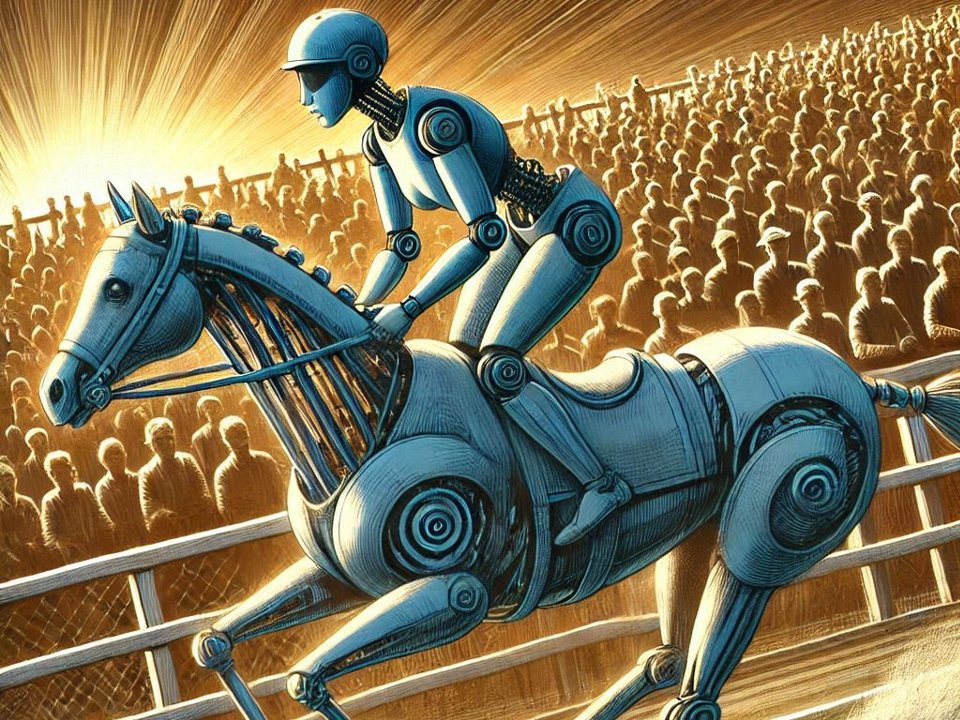


コメント